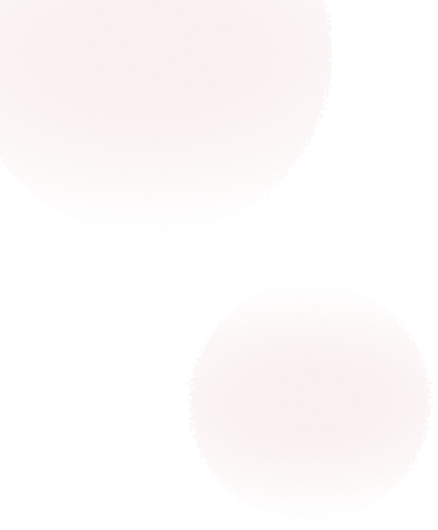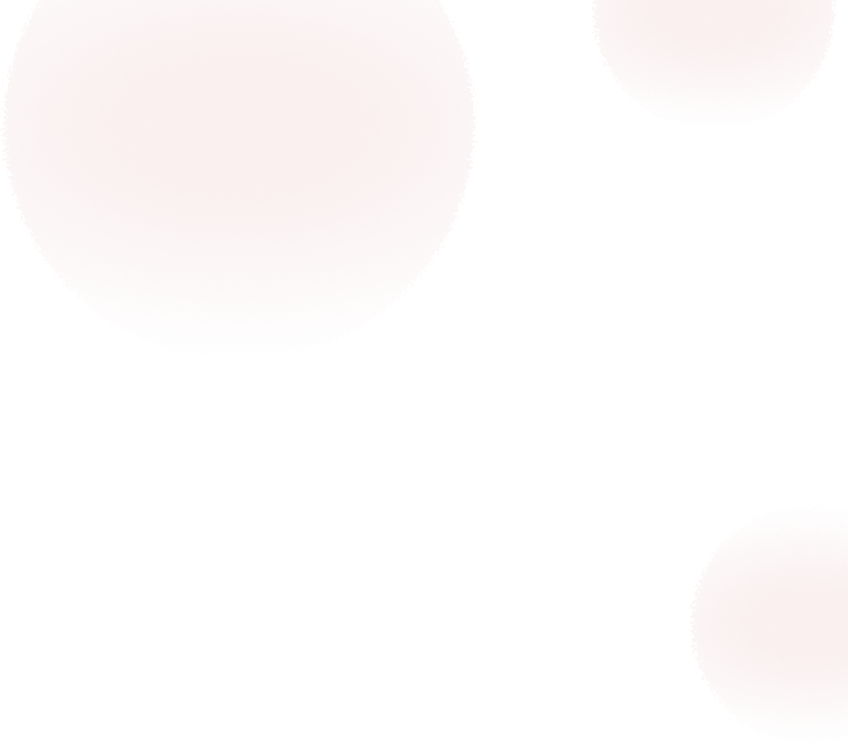PMS(月経前症候群)とは

月経前症候群(PMS:Premenstrual Syndrome)は、月経の前に心や体にさまざまな不調があらわれる状態を指します。症状は月経の3〜10日ほど前から始まり、月経が始まると自然に落ち着くのが特徴です。
日本人女性の約70〜80%が月経前に何らかの不調を感じているとされ、そのうち約5%の方は「日常生活に支障をきたすほど強い症状(重度のPMS)」を経験しています。特に思春期から20代にかけての女性に多いといわれていますが、30代・40代でも少なくありません。
PMSの診断基準
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 症状の 時期 |
月経前(排卵後〜月経開始まで)に症状が出て、月経開始とともに軽快・消失する |
| 症状の 種類 |
◎精神的症状
◎身体的症状 |
| 症状の 強さ |
少なくとも「精神的症状1つ以上」+「身体的症状1つ以上」があり、日常生活(仕事・学業・家庭)に支障が出ている |
| 症状の 持続 |
連続した2周期以上で同じような症状がみられる |
| 除外診断 | 他の病気(うつ病、不安障害、甲状腺疾患など)が原因ではない |
簡単セルフチェック
- ■次の項目に2つ以上当てはまる方は、PMSの可能性があります。
-
- 月経前になると気分が落ち込んだり、イライラしやすい
- 乳房が張る、体がむくむ、頭痛や腹痛が強くなる
- 月経前は仕事や勉強に集中できない
- 月経が始まると症状が和らぐ
- このような症状が毎月のように繰り返されている
生活に支障がある場合は「我慢せずに婦人科に相談すること」が大切です。
生理前に起こりやすいPMS症状と原因
PMSの症状は、排卵から月経までの間に繰り返しあらわれることが特徴です。その背景には、月経をコントロールしている女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の変化が深く関わっていると考えられています。
ただし、原因は単純ではなく、ホルモンや神経の働き、さらにはストレスや生活習慣など、複数の要因が影響し合って症状が出るといわれています。
ここでは、月経前に起こりやすい代表的なPMS症状と原因をくわしく紹介します。
下腹部痛や腰痛

月経前にあらわれる下腹部痛や腰痛は、PMSの代表的な身体症状のひとつです。この痛みには「プロスタグランジン」と呼ばれる物質が関係しています。
プロスタグランジンは本来、子宮を収縮させて経血を体外に排出する大切な役割を担っています。しかし同時に、痛み・炎症・発熱を引き起こす作用も持っているため、分泌量が増えると下腹部や腰に痛みを感じやすくなります。
特に月経が近づくとこの物質の分泌が増えるため、下腹部の鈍い痛み・腰の重だるさや痛みが強くあらわれることがあります。
気分が落ち込む、イライラする

月経前になると、気分の落ち込みやイライラ、不安感といった精神的な症状が強くあらわれることがあります。
痛みや倦怠感などの身体的な不調と同様に、こうした心の症状も原因はまだ完全には解明されていません。
有力な説としては、月経周期に伴う女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の大きな変動が、脳内の神経伝達物質に影響を与えるというものです。
-
- ・セロトニン(幸福感をつかさどる物質)
- ・γ-アミノ酪酸:GABA(不安をやわらげる物質)
特に、精神の安定に関わる、
これらの働きが低下することで、気分の不調が起こると考えられています。
精神症状が強く現れる状態をPMDD(月経前不快気分障害)と呼び、精神科や心療内科での専門的な治療が必要になる場合もあります。
胸の痛みや張り

月経前に起こりやすい胸の痛みや張り(乳房の不快感)は、PMSでよく見られる身体症状のひとつです。
この症状には、黄体ホルモン(プロゲステロン)の働きが深く関係しています。排卵後、黄体ホルモンの分泌が活発になると、乳腺内の血管が拡張し、乳腺組織が刺激されることで圧迫感や痛みが生じます。
さらに、黄体ホルモンの影響で体内に水分がたまりやすくなるため、むくみが乳房にも起こり、張りや重だるさを感じやすくなるのです。
眠気や倦怠感

月経前にあらわれる強い眠気や全身のだるさ(倦怠感)も、PMSでよくみられる症状のひとつです。
この症状には、深部体温(体の内部の温度)の変動が関係しています。通常であれば、深部体温は日中に高まり体を活動的にし、夜になると低下して自然な眠りを誘います。
ところが月経前は、「日中に深部体温が上がりにくい」「夜になっても深部体温が下がりにくい」という状態になりやすく、体内のリズムが乱れてしまいます。
その結果、日中は強い眠気やだるさを感じるのに、夜は眠りが浅く途中で目が覚めやすいといった睡眠のトラブルにつながるのです。
37度近くの発熱

月経前に37度前後の微熱や発熱感を覚える方も少なくありません。この症状の背景には、黄体ホルモン(プロゲステロン)の作用があります。
排卵後から月経までの期間は「黄体期(高温期)」と呼ばれ、この時期には妊娠をサポートするために黄体ホルモンが多く分泌されます。
このホルモンには体温を上げる働きがあるため、基礎体温が0.3〜0.6度ほど上昇し、平熱よりもやや高い状態が続くのです。
頭痛
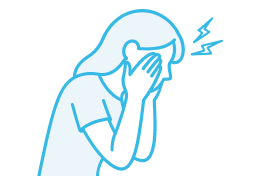
月経前になると、頭痛に悩まされる方も少なくありません。この背景には、卵胞ホルモン(エストロゲン)の急激な低下が関係しています。
エストロゲンは、脳内の神経伝達物質であるセロトニンを活性化する働きがあります。しかし月経前にエストロゲンが大きく減少すると、セロトニンがうまく働かなくなり、脳の血管が収縮と拡張を繰り返すことで頭痛を引き起こすと考えられています。
過食

月経前になると、「たくさん食べても満腹感が得られない」「甘いものや脂っこいものを無性に食べたくなる」といった過食や食欲の増加に悩む方も多くいます。
この症状には、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が関係しています。排卵後から月経前にかけて黄体ホルモンが大量に分泌されると、血糖値のコントロールが不安定になりやすくなります。
むくみ、体重増加
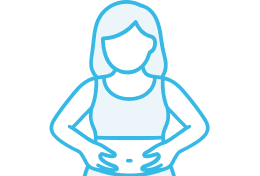
月経前になると「体が重い」「顔や足がむくむ」「体重が増えやすい」と感じる方は多いです。
この症状の主な原因は、排卵後から分泌が増える黄体ホルモン(プロゲステロン)にあります。
| 症状 | 原因・仕組み | 注意点・特徴 |
|---|---|---|
| むくみ | 黄体ホルモンが皮下細胞に水分をため込む作用を持つため、体内に余分な水分が蓄積される | 顔・手足のむくみや乳房の張りにつながりやすい |
| 食欲増進 | 黄体ホルモンの分泌により、血糖値のコントロールが不安定になる | 空腹感を感じやすく、食べる量が増えやすい |
| 胃や腸の機能低下 | 黄体ホルモンの増加で腸の運動機能が低下。 食道括約筋の緩みで、逆流性食道炎も起こりやすくなる |
胃もたれや便秘、胸やけの原因に。 一気に大量の食事を摂ることは避けたほうがよい |
PMSの治療
PMS(月経前症候群)の治療には、生活習慣の改善に加えて、症状の程度に応じて薬物療法が行われます。
低用量ピルや漢方を用いた治療
代表的な治療方法には、低用量ピル(OC・LEP)や漢方薬の服用があります。
- ■低用量ピル(OC/LEP)
-
排卵を抑えることで、月経周期に伴う女性ホルモンの大きな変動を抑制できます。そのため、むくみや胸の張り、気分の変化など、排卵後に出てきやすい症状がある場合に特に有効です。
これらの働きが低下することで、気分の不調が起こると考えられています。
- ■漢方薬
-
漢方薬は、体質や症状に合わせて処方されるため、ホルモン剤に抵抗がある方や自然に近い方法で治療を希望する方にも選ばれています。
冷え・むくみ・精神的な不調など、複数の症状に同時にアプローチできる点も特徴です。
セルフケアによる治療
PMS(月経前症候群)の症状が軽度の場合は、薬を使わずに生活習慣の工夫(セルフケア)で改善を目指すことも可能です。
- ❶自分の症状を把握する
-
まずは、PMSの症状がいつ・どのように出ているのかを知ることが大切です。
・基礎体温を記録する
・月経前に起こる不調(頭痛・気分の落ち込み・むくみなど)を書き出す
このように記録を続けることで、自分のPMS症状の特徴や傾向が分かり、セルフケアや医療機関の受診判断にも役立ちます。
- ❷食生活を整える
-
・カルシウム・マグネシウム:神経の安定や筋肉の緊張緩和に役立
・カフェイン・アルコール:摂りすぎは症状を悪化させるため控えめに
・喫煙:可能な限り控える
栄養バランスを意識することで、心身の不調を和らげやすくなります。
- ❸リフレッシュ習慣を取り入れる
-
・ゆっくり湯船につかる
・軽い運動やストレッチをする
・趣味やリラクゼーションで気分転換をする
自分が「心地よい」と感じる習慣を取り入れ、無理のない範囲で継続することが大切です。
PMDD(月経前不快気分障害)とは?PMSとの違い
PMSの中でも精神的な症状が特に強く現れる状態をPMDDと呼びます。精神医学的には「うつ病」と同じ抑うつ障害群の一つに分類される病気です。
- ■具体的には以下のような症状が強く出るのが特徴です。
-
・強いイライラや攻撃的な言動
・ネガティブな思考が止まらない
・不安感や気分の落ち込み
・人間関係や仕事・学業に支障が出るほどの精神的不調
PMSとPMDDの違い
| PMS | PMDD | |
|---|---|---|
| 主な症状 | 身体症状+軽度〜中等度の精神症状 | 強い精神症状が中心 |
| 生活への影響 | 不快感はあるが日常生活に大きな支障は少ない | 人間関係や仕事・日常生活に深刻な影響を与える |
| 医学的分類 | 婦人科領域で扱う症状 | 精神科領域でも「抑うつ障害群」に分類される病気 |
PMS(生理前症候群)は我慢せずにご相談を

月経に関わる心身の不調は、「仕方のないこと」と思って我慢してしまう方も少なくありません。しかし、実際にはPMS(月経前症候群)を含む多くの月経関連症状は、婦人科で治療が可能です。
PMSは月経前の数日〜10日間ほどに起こるため、つい「すぐに治まるから」と放置してしまうケースが多いのが現状です。ですが、もし月経前に毎回10日間不調を感じているとしたら、1年間で約120日、つまり 1年の3分の1をつらい気持ちで過ごしていることになります。
このように長期間にわたって心身に負担をかけてしまうと、日常生活や人間関係、仕事・学業にも影響を及ぼしかねません。閉経まで長く付き合っていく女性のからだだからこそ、「我慢する」よりも「治療する」選択をしてみませんか。
どうぞお気軽にご相談ください。
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15:00-19:00 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
●:初診・再診
▲:予約再診のみ
★:17:00まで
×:休診(土/日曜日の午後、祝日)
※診療受付は終了30分前までです。
※日曜日は体外受精、人工授精のみ完全予約制です。