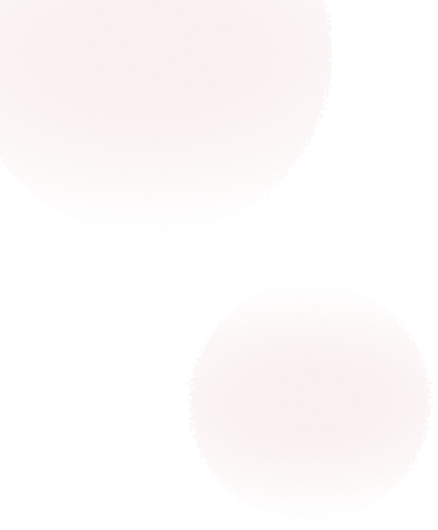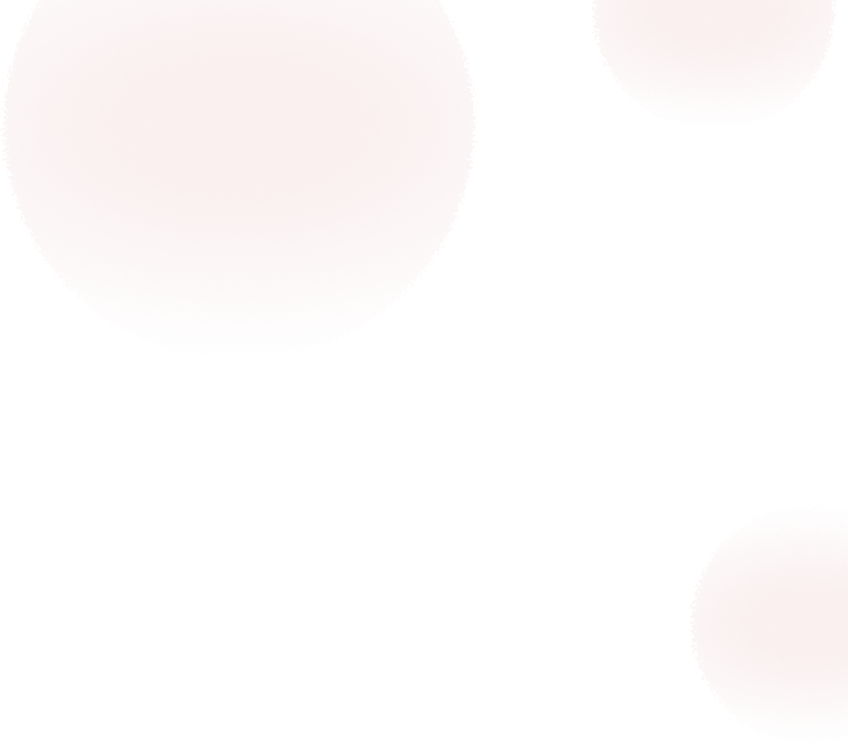男性の不妊症について

男性不妊の約90%は、精子をつくる機能に障害がある「造精機能障害」とされています。さらにこの造精機能障害は、原因が特定できるものと、原因が不明なものに分かれます。
造精機能障害(原因あり)
- ■身体的な要因が明らかになっているケースです。
-
・精索静脈瘤
・Klinefelter(クラインフェルター)症候群やその他の染色体異常
・両側の停留精巣(精巣が正しく降りていない状態)
・悪性腫瘍の手術後
・耳下腺炎(おたふくかぜ)による精巣炎など
造精機能障害(原因不明)
約半数のケースでは明確な原因が見つかりませんが、以下のような要因が関与していると考えられています。
- ・ストレスや過度のアルコール摂取
- ・喫煙習慣
- ・肥満・糖尿病などの生活習慣病
- ・一部の薬剤や持病の影響
- ・精巣への外傷や炎症など
非造精機能障害(約10%)
これは精子の通り道や射精に関わる機能に障害がある場合です。
- ・精管や精嚢の閉塞性障害
- ・勃起不全、射精障害などの性機能障害
このように、男性不妊にも多くの原因があり、造精機能障害が大部分を占めることがわかっています。原因が不明でも、治療によって妊娠の可能性が高まるケースもありますので、気になる方は早めの検査とご相談をおすすめします。
男性不妊治療の流れ
1. 精液検査
まずは精液の状態を調べる検査を行います。精子の数・動き・形などを評価し、不妊の原因を把握します。
2. 必要に応じた追加検査
検査結果によっては、以下のような追加検査を行います。
- ・ホルモン検査(男性ホルモンなどの分泌状況を確認)
- ・超音波検査(精索静脈瘤の有無を確認)
- ・染色体検査(異常が疑われる場合)
3. 治療の選択
検査結果をもとに、以下のような治療法から適切な方法を選択します。
- ・薬物療法:ホルモンバランスの調整や精子の質の改善
- ・外科的手術:精索静脈瘤の修復など
- ・生殖補助医療(ART):人工授精、体外受精、顕微授精など
精液所見からみた主な原因と特徴
精液検査の結果は、WHOのガイドライン(2020年)に基づいて評価され、不妊の原因を特定する手がかりとなります。
乏精子症(ぼうせいししょう)
精子の濃度が15×10⁶/mL以下
精液中に精子は存在するが、その数が少ない状態です。軽度であれば自然妊娠が可能な場合もありますが、重度の場合は顕微授精が必要となることがあります。
精子無力症(せいしむりょくしょう)
総運動率が40%以下、または前進運動精子が32%未満
精子の数は正常でも、動きが弱く受精に至りにくい状態です。重度の場合には顕微授精を行うケースもあります。
精子奇形症(せいしきけいしょう)
正常な形態の精子が4%以下
精液中にはもともと奇形精子が多く含まれますが、正常形態精子が5%未満の場合は受精能力が低く、顕微授精が推奨されることがあります。
無精子症(むせいししょう)
射出された精液中に精子が全く認められない状態
男性不妊の中でも重度の症状で、精巣で精子がつくられていない、または精子の通り道に閉塞があることが原因です。追加の検査や外科的治療が必要になる場合があります。
これらの所見によって、治療方針や妊娠に向けたステップが大きく異なります。ご不安な点があれば、医師がわかりやすくご説明いたしますので、どうぞご相談ください。
主な治療法
薬物療法

ホルモンバランスの調整や精子の質の改善を目的として行う治療です。
男性ホルモンの分泌が不足している場合や、精子の運動率・濃度の低下がみられるケースで用いられます。ビタミン製剤やホルモン剤などを服用することで、精子をつくる力を高める効果が期待できます。
外科的手術

精索静脈瘤の修復など、明確な身体的な原因がある場合に行います。
精索静脈瘤とは、精巣周辺の静脈にこぶのようなふくらみができる状態で、精子の質を低下させる原因の一つとされています。
顕微鏡を用いた低侵襲な手術で静脈の逆流を防ぐことで、精子の状態が改善する可能性があります。
生殖補助医療(ART)
自然妊娠が難しい場合に行う高度な治療法です。状態に応じて選択されます。
- ■人工授精(AIH)
-
採取した精子を洗浄・濃縮し、排卵のタイミングに合わせて子宮内に注入する方法です。卵管を通して自然な受精を促すため、比較的身体への負担が少なく、自然妊娠に近い形での治療といえます。
- ■体外受精(IVF)
-
排卵誘発で採取した卵子と、採取した精子を体外で受精させたあと、受精卵を子宮に戻す方法です。受精の過程を体外で管理できるため、卵管の異常や重度の男性不妊にも対応可能な治療です。
- ■顕微授精(ICSI)
-
1つの卵子に対して1つの精子を顕微鏡下で直接注入する方法です。精子の数が極端に少ない、運動率が著しく低いなど、重度の男性不妊に対して有効な治療法です。
いずれの方法も、ご夫婦の状態や希望に応じて慎重に検討・ご提案いたします。治療の内容や流れについても、わかりやすく丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
酸化ストレスと男性不妊について
酸化ストレスとは?

私たちの体の中では、普段の生活の中で「活性酸素」という物質がつくられています。
活性酸素は体を守る働きもありますが、多くなりすぎると体の細胞を傷つけてしまいます。このように、活性酸素が増えすぎて体に悪影響を与えている状態を「酸化ストレス」と呼びます。
酸化ストレスが増える原因
- ■生活習慣や環境によって、酸化ストレスは高まりやすくなります。
-
- ・喫煙や過度の飲酒
- ・睡眠不足やストレス
- ・熱がこもりやすい下着や長時間の座りっぱなし
- ・肥満や運動不足
こうした習慣がある方は、知らないうちに精子がダメージを受けている可能性もあります。
検査でわかることも
通常の精液検査だけでは酸化ストレスまではわかりませんが、最近では以下のような精子の質を詳しく調べる検査もあります。
ORP検査(酸化ストレスを数値で評価)やDFI検査(精子のDNAがどのくらい傷ついているかをチェック)によって、精子の「見えないダメージ」を把握し、治療方針を立てることができます。
酸化ストレスを減らすには?
- ■まずは日常生活の見直しがとても大切です。
-
- ・バランスの良い食事
- ・十分な睡眠
- ・禁煙/節酒
- ・ストレスをためない生活
- ・ゆったりとした服装、適度な運動
さらに、ビタミンC・E、亜鉛、コエンザイムQ10などの抗酸化成分をとることも、精子のダメージを減らす助けになります。また、「精索静脈瘤」という静脈のトラブルがある場合は、手術によって酸化ストレスが改善し、精子の質が良くなることもあります。
酸化ストレスは、見た目ではわからないけれど、男性不妊に深く関係している重要な要素です。生活習慣の改善や必要な検査・治療を組み合わせることで、妊娠の可能性を高めることができます。
「検査で異常がなかったのに、なかなか妊娠しない」という方も、一度酸化ストレスの影響を見直してみると良いかもしれません。
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15:00-19:00 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
●:初診・再診
▲:予約再診のみ
★:17:00まで
×:休診(土/日曜日の午後、祝日)
※診療受付は終了30分前までです。
※日曜日は体外受精、人工授精のみ完全予約制です。